2015年10月05日
水路の魚たち
どんな魚が居るのか毎年調べているのですが、年々個体数と魚種が少なくなっています。
今年はビワヒガイが一番多く、次がタモロコ(画像なし)。ウグイはとても少なかったです。
ウグイは流れがある場所を好む魚ですから、川の流れがおかしくなって、個体数が減少しているのかもしれません。
今まで確認できたウケクチウグイもここ数年姿をみていませんから心配です。
ウグイと鯉。左下ビワヒガイ。右下ニゴイの幼魚。

取り残された小魚が居るマスは、カワセミやサギの冬場の餌になっているようです。
2015年09月19日
2015年09月15日
湯殿山大日坊大蔵出張所跡地.2 珪化木
遠目にも直ぐに珪化木だと気付きました。

近所の人が他意はなく置いただけだと思いますが、この色、この珪化木の産出地が何処なのか凄く気になりました。
2012年03月20日「木の化石 珪化木」を読み返すと、大蔵村南山地区で産出するようです。ってエリア広過ぎ!
清川〜立谷沢川〜羽黒山スキー場第二駐車場トイレ脇までホタテ貝。
戸沢村と真室川町では海牛や鯨の化石が見つかっており、その昔は周囲は海のはず。
太古の昔の地形を教えてくれることも化石のロマンです♪ 
吹浦駅前にある遊佐町の観光案内図に女鹿駅が載って無いように
大蔵村HPでは歴史ある湯殿山大日坊大蔵出張所跡地を紹介していません。
大蔵村教育委員会が湯殿山大日坊大蔵出張所跡地の看板を掲げているのですから、紹介すべきでしょ。
「稲沢の渡公園」の向かいなのですから。

2015年09月14日
湯殿山大日坊大蔵出張所跡地.1
http://www.dainichibou.or.jp/
http://www.asahi-kankou.jp/kankou/member5.html
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0141.html
http://yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=1534
大日坊に出入りしていると(遊ばせてもらっているといると)耳に入する大日坊大蔵出張所へ、やっと行ってきました。

此処から舟で最上川を下り、清川で下船して羽黒山を通り大日坊なのでしょうか。歩けば未だ未だ遠い道のりですね。
2015年08月27日
アシナガバチ
これは近くに巣があるときの行動なので急いで下がりました。距離をとって周囲を見渡すと、大きな巣がありました。


山での発見ですし、他の人が刺される危険性は少ないので、駆除せず放置です。
2015年07月28日
コウモリ
大きな蛾が飛び込んできたのではないかと思い、慌てて覗いて観ると、真っ黒い変なのがバタバタ暴れていました。
「バタバタ暴れていた」と感じたけど、べちゃべちゃという湿めった音感で、よ〜く観てみると、コウモリでした。
ステンレスの支柱に止ろうとして、掴まり損ねて落下したのでしょうか。近づくと這って物陰に隠れてしまいました。


サイズ的に小さいので今年生まれたばかりでしょうか。その場から離れると直ぐに出てきて飛んで行きました。
2015年06月16日
自然学習と自然保護
イバラトミヨの産卵期は5〜6月頃。産卵には枯れ草で巣を作るというのに、17名以上の人間が生息地に入り込めば
営巣に適した水草を踏み倒し、巣作りの材料となる細い繊維状の枯れ草を流失させることになります。
捕えられたイバラトミヨは学校で飼育され学習に役立っても、生息地の環境は破壊され、営巣数も減ることでしょう。
土地改良区は水路の改築工事の際には「メダカ救出作戦」と称して、地元小学生を利用したイベントを行い、
用水路にU字溝を設置して三面コンクリート張りにしてしまいますが
メダカは生息環境の悪化が原因で絶滅危惧種に指定されているのであって、メダカを救出するのは本末転倒なこと。
それなのに山形新聞は子供の笑顔の写真を使い、「捕えた個体は学校で役立てる」という論点の差し替えを毎回工作。
企画する県や公共機関、これを明る地方ニュースと取り上げるメディアの姿勢には、いつも悩まされます。

「自然に関心がある」という一般の方は、カワセミや鮎をみつければ「自然が帰ってきた♪」と喜ぶ人が大半ですが
実際にはカワセミや鮎などは何所にでも居るし、その逆に彼らは行く場所がないからそこに居るとも言えるわけで、
「自然に関心がある」なら尚更「木を見て森を見ず」にならないよう、留意していかないといけないのではないでしょうか。
一喜一憂する姿は、県や公共機関+マスコミに利用されやすいのですから。
2015年05月28日
アオオビハエトリ
最初は甲虫の一種だと思ったのですが、気のせいか輝いて見えて、停車してよく視てみると蜘蛛じゃないですか。
初めて見たので写真を撮り、外に放してやりました。

2015年05月27日
アラメ 飛島にもあるよ
http://www6.nhk.or.jp/umai/archive/
↑
佐渡島のアラメが紹介されていました。ネット動画検索すると視られます。
アラメ漁は飛島でも行われ、生産しています。地産地消、みなさん食べてね♪

笹団子にアラメを入れてましたが、飛島でも工夫が必要かもしれません。

閑話:飛島の干し柿は異常なまでに甘くて美味かった。どうしてあれだけ甘くなるのか不思議です。
あれはあれで特産として売れると思うんですよね。私なら買います。上ノ山の干し柿より断然甘くて美味かったです!
2015年05月25日
幻の女鹿駅
吹浦駅前の看板が新しくなっても、未だ幻の女鹿駅。

昔、朝日村観光パンフレットに湯殿山スキー学校が記載されていませんでした。
朝日村役場に問い合わせると
「湯殿山スキー学校は朝日村観光協会に加盟してないので、掲載してません」
と言われたことがあった。
湯殿山スキー学校は商売だから、その説明に納得したが、女鹿駅は公共施設でもあり、掲載しないことが理解できない。
遊佐町役場企画課は無能で、NPO遊佐鳥海観光協会は馬鹿なのかな・・・。悲しくなるよ。

2015年05月18日
2015年04月28日
2015年04月16日
プラントハンター 西畠清順
~プラントハンター 世界を行く~
プラントハンター 西畠清順
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2015/0328/

番組内容的には賞賛しているけど、貴重な植物を採ってきて見せ物にしているわけです。
西畠氏はプラントハントを「家畜を屠殺したり花屋で花を買うのと同じだ」と主張していますが、それらは農業。
彼の行為はタラの枝を切るのと同じ山採りなわけで、採ったら終わりの行為は活け花ではありません。
それがもてはやされるようで不快な気持ちになりました。それで良いのでしょうか・・・。
やはり快く思ってない人も少なからずいるようで安堵しました。
↓
話題のプラントハンター
http://bluejay100.blog.fc2.com/blog-entry-12.html
2015年04月05日
2015年03月23日
コシノコバイモ


コシノコバイモは順調に成長しても、少なくとも6ないし7年はかかって成長し、開花・結実して、次世代個体を生み出している。
http://www.osaka-gu.ac.jp/research/research/pdf/h20/hayashi.pdf
このように6-7年も掛かって開花する準絶滅危惧種に指定されたコシノコバイモを盗掘してネット販売するのは如何なものでしょう。

このネットショップでは桜草も販売していますが、真っ赤な偽物。
月山に自生地はありませんし、
林道工事がかかる場所に桜草は自生しません。
しかも種採り育成なんて荒唐無稽な話しです。
以前は赤花だけなのに、いつのかにもか白い桜草まで持ち出して、とんでもない詐欺商法です。
山採り盗掘して商売するのは止めてほしいし、モラルあるユーザーは、決して購入しないでください。

2015年03月16日
片野修 著「河川中流域の魚類生態学」
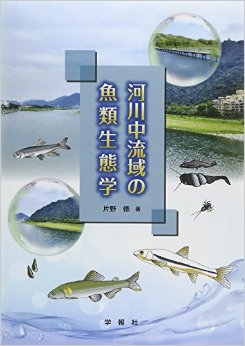
自然環境と保全を語るとき、特徴的な場所や生物がフォーカスされ題材として取り上げることが多い。
それは読み手として関心事項に特化したタイトルと内容なら選択して購入しやすしく、楽しく読めるのだが
生き物は連鎖であり生態系と多様性が肝要なのに、それが省いて論ずる事になってしまいかねない。
国定公園や世界遺産、ラムサール条約に登録した自然豊かな場所を題材に自然環境と保全を語られてもピン!とこないし
サクラマスや鮭の稚魚やホタルの幼虫を放流したりと、1つの生き物だけを取り上げて、なにが働くというのだろう。
川の流れに勢いがなく、瀬なのか淵なのか、緩急の見分けが付かない。
町を流れる川は「美しい!」「自然豊かだ!」と言えそうで言えない今の状況でも
地元の河川だもの、そこの自然環境と生態系は守りたい。
でも何をどうしたらいいのか、我々には肝腎な箇所がぼやけてしまって判らないでいる。
河川管理を行う行政は解っているから河川改修を押し進めていくというのに・・・。
行政が河川改修を行う場合、民意を反映しようと説明会を開会したり広く意見を募集するが
見識が浅い我々一般人は
「自然に配慮した工事と川造りをお願いします」
「魚が住める川造りをお願いします」
と、常に抽象的で曖昧な文言でしかお願いが言えないでいる。
では具体的に願う「自然に配慮した川造り」「魚が住める川造り」の形は何なのか!?
その参考となる内容が、この本には書かれており、とても勉強になった。
赤川でも鮎が釣れなくなり、
「河床が低下して鮎が縄張りを張る石が無くなったから、川に大きな石を入れて、釣れるようにしてくれ!」
と、目先の釣果という己の願望のみで単略的な意見を述べる赤川漁協組合員が未だに居たりするが
どういう川造りを目指すのか、釣り人として共通の見識を持つためにも、ぜひ多くの人に読んでほしい1冊です!
片野修氏の本は一度紹介したことがある。
「アユの科学と釣り―美しい川とアユを願って」
著者は鮎釣り師でもあるが、釣りと鮎と生態系を多くの人の声を加えて書かれており、面白くためになるので
この手の本としては珍しく売り切れになったはず。
釣友は「注文したけど品切れだった」と言っていたのだが、アマゾンに新品が1冊残っていた。お薦めです♪

ほかにもカワムツやナマズといったマイナーな魚を取り上げた本が出版されていますが、
実はこれらの魚は清流=中流の魚なんですよね。
ナマズを田んぼの魚というイメージから泥を好むと思われがちですが、綺麗な砂礫の川を好みます。
赤川の梵字川や大鳥川はナマズが多く生息して、とくに大鳥川は宝庫でした。
釣りの対象となる魚の釣果は、漁協の放流数で変動可能なので、環境の指針にはなりませんが
放流されていない天然の魚種は河川環境の大切な指針です。
川が綺麗かそうではないのかは、魚が教えてくれます。
中流域の砂礫の川底の大切さを、私たちは忘れてはいけないと考えます。

2015年03月15日
砂丘の暴走
鳥取砂丘の中心部は国の天然記念物で、うち131ヘクタールが特別保護地区に指定され車馬の乗り入れが規制されている。3人は「乗り入れ禁止とは知らなかった」と話していたという。県砂丘事務所の堀田利明所長は「現場を含め、各所に乗り入れ禁止の看板があるが、数年に一度、同様の被害がある。云々」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150314-00000040-asahi-soci

2008年10月11日『俺じゃない』
庄内砂丘も「庄内海浜県立自然公園」なのだが、一向に非常識な暴走行為は止まないし、
風雨になればワダチが消えるような状況もないというのに、通報しても警察は動かない。
暴走する非常識な人が悪いのだけど、こういう記事を読むと、通報しても動かない警察を非難したくなる。
対応が妙に素直で神妙だと感じていたら、“犯人”は消防士だったようです。
庄内砂丘を暴走する輩は質が悪く、福島県や宮城県から愛好者を募って暴走してますからね。
鳥取砂丘の特別保護区、車で蛇行1.3キロ “犯人”は兵庫の消防士3人 処分も検討
産経新聞 3月20日(金)12時3分配信
鳥取砂丘(鳥取市浜坂)で14日、観光客の男性3人が、車の乗り入れが禁止されているエリアに車で乗り入れた問題で、3人が兵庫県内の消防で勤務する消防士だったことが20日、分かった。
各消防によると、3人は同県三木市消防本部の男性消防士(19)と、同県姫路市消防局と同県南但消防本部(朝来市)の男性消防士2人=いずれも(21)。友人同士で休日を利用して訪れていた。各消防は処分を検討している。
鳥取県警などによると、3人は14日、鳥取砂丘の「特別保護地区」に当たる場所に車で乗り入れ、蛇行や旋回をしながら約1.3キロを走行したとされる。県警は自然公園法違反の疑いがあることから、3人に事情を聴いていた。
2015年02月26日
上海ガニ
上海ガニ無許可で“飼育”全国で“初摘発” 日本テレビ系(NNN) 2月20日(金)16時30分配信
上海ガニを許可なく販売目的で飼育したなどとして、警視庁は中国人の男らを書類送検した。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150220-00000025-nnn-soci

2015年02月11日
マルハナバチの一生
桜草の自生に大きく関係するマルハナバチ。舞台は外国ですが、桜草栽培者は必ず観てね。
南アルプスを縦走した時もトリカブトにマルハナバチがとまってました。

サクラソウの目: 繁殖と保全の生態学 - 鷲谷いづみ
http://www.chijinshokan.co.jp/Books/ISBN4-8052-0775-2.htm

2009年01月19日『日本桜草の本』
2009年01月30日『日本桜草の本.3』
『サクラソウの分子遺伝生態学 エコゲノム・プロジェクトの黎明 - 鷲谷いづみ』
2009年01月30日『ハプロタイプπ』
鷲谷いづみ著『サクラソウの分子遺伝生態学 エコゲノム・プロジェクトの黎明』に書かれていることは、だいたいこんな内容です。
2009年01月31日『横山潤准教授』
今朝の山形新聞朝刊を見ていると、19面に、日本桜草の花の写真掲載されていた。
山形大学理学部生物学科横山潤准教授の項で、マルハナバチも研究対象らしい。
2015年02月04日
新デザインの普通切手
2014年11月12日、日本郵便は普通切手のデザインを変更し2015年2月2日から発行することを発表した。普通切手はデザインの統一性を図ることを計画していることが過去に発表されていたが、2014年の新料金からデザインテーマ「日本の自然」で発行がされており、額面により詳細テーマが示されている。
http://yubin.2-d.jp/y1/19.html









