2017年10月31日
アオリイカ釣りの仕掛け
アタリが全然少なかったのでウキ釣りだけで行ないました。
それなりに反応が有ったら試したかったのが、
ミヤエポック(Miya Epoch) イカハンターシリーズ 錨の又三郎。
跳ね上げ式じゃないので跳ね上げ式に改造したり、そのまま足元で釣るのには良さそう。

活アジを使ったアオリイカのウキ釣り仕掛けを使ってみた印象は下記の通り。
・ウキはフカセ釣りの細い電気ウキは2箇所で灯るので、アタリをとりやすい。
・鼻カンと背カンの2種類あるが、背針の方が取り付けやすく、支点が高くなるので掛かりも良さそう。
背カンの方が良く泳ぎ,姿勢も良かったです。
・ウキが沈むくらい元気に泳ぐアジの方が釣れそうでした。
・アジが弱ると海面近くに漂い潜行しなくなるので、オモリを付けて沈ませないといけないようです。
でも、そんなことするくらいなら活きの良いアジに付け替えた方が良い。その辺りは鮎の友釣りみたいでした。
・針は2段とV型があり、今回は釣果尾数が少な過ぎて、どちらが良いか判断つきませんでした。
・がまかつの緑色のV型「お墨つきアオリイカ仕掛 はねあげ式 45553」は、やたらフグが掛かり駄目。
V字の接点を固定するためと針が抜けないよう針尻に、接着剤が夜光の極小の玉となって付いているのですが
それをフグたちが餌だと勘違いして幾度となく引っ掛かるのです。
その都度仕掛けを回収していると餌であるアジが弱まるし、アジもフグに襲われて外れてしまうようです。
他社の仕掛けにフグは掛かりませんでしたから、緑色と夜光の極小の玉が原因だと感じた次第です。
・ヤマシタ「 イカ泳がせ仕掛 しなやか」は、活アジを付ける箇所が固定されており・・・
アジを取り付ける際に手や服の袖口に引っ掛かって大変で、カエシ付きなので外すのにひと苦労しました。
でも掛かりは良さそうです!
ハリミツでは「ハナカン」「エサ針」という表記になっています。
エサ針=背カン(背針)なので、個人的にはコチラが好みです。
ハリミツの泳がせウキ釣りセット
V-31E アオリイカ うき釣 2段 エサ針
V-31H アオリイカうき釣 2段 ハナカン
V-3E アオリイカうき釣 V型 エサ針
V-3H アオリイカ うき釣 V型 ハナカン
電気ウキ所有者ならハリミツの泳がせ
2017年10月31日
飛島でアオリイカ釣り
という天気予報を信じて飛島へ行ってきました。
今回の目的はズバリ「アオリイカの餌釣り!」
2013年に飛島に滞在した時、私はエギングを楽しむつもりでしたが、
同行者が釣り経験0だったため、彼のために私はハリミツの「アオリイカのウキ釣り仕掛け」を準備しました。
サビキでアジを釣り、活きたアジを餌にアオリイカを釣るウキ釣り仕掛けです。
そしていざやってみると、仕掛け投入と同時に間髪入れずアオリイカが襲ってきました。
そのアタリは強烈で、置き竿にすると竿を持って行く勢いがありました。
まさかこんなに高反応だとは思っても見なかったんで、「アオリイカのウキ釣り」を勉強してなかった私は
強烈な引きにアワセを入れてしまい、ほぼスカしてしまいました。
帰宅後に調べたら、ヤエン釣りの要領で、ゆっくり引き寄せながら針掛かりを待つ釣りでした。
今回はそれを再度試すべく飛島へ渡りました。
フェリーは予想に反して、台風21号通過後のタイミングに合わせた大勢の釣り人で賑わってました。
それと酒田市議会選挙の繰り上げ投票のために投票箱を持ち帰るため酒田市の選挙委員会の方も乗っていました。
『あれれ、それって海が荒れるってこと???』
港の沖堤へ渡るため渡船を有している民宿あづま屋を予約したのですが、行って見てびっくり。
民宿あづま屋さんは飛島で唯一のラーメン屋で、ラーメン店の二階が部屋だったからです。でもとても快適でした。
お昼はラーメンを食べて港でアジ釣り。
コマセを撒くとフグの猛攻にあいましたが、徐々にアジが寄ってきてそれなりに釣ることが出来ました。
途中3組のエギング愛好者が合われてましたが、「魚影が全然みえない」と言って早々に去って行きました。
晩飯後、活かして置いたアジを餌に「アオリイカのウキ釣り」を開始。
風が強くて『この場所はよろしくない』と感じましたが、
活かしたアジを持って移動することが面倒なので、そこで粘ることに。
幸い同行者が1杯釣りました。
宿に戻ると「えっ、イカ釣れた!?」「最近は全く釣れてなかったんだよ。」とのこと。
アジを餌に釣ったと伝えると「エギじゃなくて?」「アジで釣る?」「そんな話し始めて聞いた」
と驚かれていました。
二日目の夜はもっと強風。荒れる港で先ずはアジ釣り。前日より好い感じでアジが釣れてくれました。
アオリイカは同行者が1杯釣り、私にもアタリましたが、
あまりの強風でアワセのタイミングが今イチ判らず、バレてしまいました。
その晩はあづま屋の息子さんたちがエギングに出掛け、ラン&ガンで800gを2杯と600gを1杯釣りました。
我々の初日のアオリイカは調理して食べてしまいましたが、女将さんいわく600gほどだったそうです。
今回は台風22号の影響で風が強過ぎて満足に攻めることができませんでしたが、
活きアジを餌にアオリイカ釣りを楽しむ事は可能でした。またいつか、挑戦したいと思います。

飛島の発電所勤務の方いわく、飛島のエギングは「去年よりは良いけど、今は釣れない」とか。
岸壁のあちこちに墨跡はありましたが、今年の飛島のアオリイカは今イチ不漁だったようです。
私はフカセ釣りをやったことがないので、細い電気ウキを持っていないので、
ハリミツのアオリイカウキ釣りセットを使いました。
フカセ釣りの細い電気ウキは2箇所で灯るので、アタリをとりやすそうでした。
これら泳がせ釣りの仕掛けには餌であるアジを取り付けるのに,鼻カンと背針の2種類ありますが、
背針の方が取り付けやすく、泳ぎも良かったです。支点が高くなるので掛かりも良さそうです。
針は2段とV型があり、今回は釣果尾数が少な過ぎて、どちらが良いか判断つきませんでした。
ただし、がまかつの緑色のV型「お墨つきアオリイカ仕掛 はねあげ式 45553」は止めた方が良いです。
V字の接点を固定するためと針が抜けないよう針尻に、接着剤が夜光の極小の玉となって付いているのですが
それをフグたちが餌だと勘違いして幾度となく引っ掛かるのです。
その都度仕掛けを回収していると餌であるアジが弱まるし、アジもフグに襲われて外れてしまうようです。
他社の仕掛けにフグは掛かりませんでしたから、緑色と夜光の極小の玉が原因だと感じた次第です。
ヤマシタ「 イカ泳がせ仕掛 しなやか」は、活アジを付ける箇所が固定されており・・・
アジを取り付ける際に手や服の袖口に引っ掛かって大変で、カエシ付きなので外すのにひと苦労しました。
ハリミツの泳がせウキ釣りセット
V-31E アオリイカ うき釣 2段 エサ針
V-31H アオリイカうき釣 2段 ハナカン
V-3E アオリイカうき釣 V型 エサ針
V-3H アオリイカ うき釣 V型 ハナカン
電気ウキ所有者ならハリミツの泳がせ
2017年10月30日
木の化石 珪化木
大木の根に抑えられているのが珪化木。&以前見つけて流失しないよう川岸へ放っておいた珪化木。

↓2012年03月20日「木の化石 珪化木」で紹介した珪化木。
持とうと思えば持てそうだけど、挑戦すると腰を痛めそうな微妙な重さ。
流されそうになったので岸に移動したけど、逆に落葉で埋まりそうですね。(^^;

2017年10月30日
温海温泉の珪化木
最初は『妙に細い門柱だな』と思ったが、車で通り過ぎた時に珪化木だと気付いた。
その時は狭い集落の道であることと、なにせ家の前であるので、写真を撮ることもなく通り過ぎてしまった。
先日、再びその前を通ったのだが、それは無くなっていた。
やはりあの時立ち寄っていれば良かったと後悔した。残念。
代わりに在ったのが下記の太い珪化木。見事である。


この集落の近くで珪化木が産出するとは知らなかったし、
普通集落内で産出される場合は他の軒先きにも置かれているものだが
珪化木を置いているのはこの1軒だけというのも気になり、今回は図々しくも訪ねてみることにした。
しかし既にこの家は空き家になっていた。
こんなに太くて立派な珪化木だもの、隣りの人が何か事情を知っているかもしれない。悩んだ末に突撃させて貰う。
あれ、↓コレは珪化木では!?
間違いない。木の根元の珪化木だ。お隣り同士で珪化木を所有しているということは、この集落で産出るんだ。
しかもみんな大きい!・・・でもこの1個だけ???

突然の訪問者に対応してくれたのは、高齢の爺さんだったが、
珪化木に気付いてもらえたのが嬉しかったのか、明るく対応してもらえた。
聞けば珪化木はこの辺では産出されておらず、他の場所から持ってきたとのこと。
この珪化木の色合いに見覚えがあるので
「この↑木の根元の珪化木は○○から採ってきたのですか?」とズバリ地名を言って尋ねると、
「うん、そうだ」とのことだった。
とはいえ○○地区の具体的産出地点が判らないので、具体的に何処で見つけたのか突っ込んで質問してみると
「前は土建業者でユンボを運転していて、○○地区の○○を掘れば出てきたもんだ」との教えてくれた。
合点がいった。○○地区には家の前に珪化木を置いている家は多いのに、住民は珪化木に疎い人が多かった。
時々産出した分けではなく、こういう工事中に産出するだけだったから、地域に珪化木が浸透しなかったのだろう。
2009年10月15日「立谷沢川の夢は幻.2」同様、化石は地中深くに眠っているんですね。
掘削工事現場に行けば、見つけられる可能性は大きいとも言えそうです。(^^;

お爺さんは話しをしながら植木鉢を持ち上げ、「こんなも珪化木だ」と言って次々見せてくれたが、
全てサイズが大きくないし、○○地区の珪化木とは違うようなので、「これは何処で?」と尋ねると
「ほれ、温海の川の温泉の所のだ」と教えてくれたが、『温海の川の温泉の所』が判らない。
判ったとして、どうせ温泉街を流れる温海川の護岸工事か何かの掘削工事中にでも見つけたのだろうから
具体的な場所を知っても採りに行けないと思い、それ以上は聞かなかったが、
温海温泉で珪化木が産出するとは知らなかった。図々しくも訪ねてみて正解でした。
肝腎のお隣りの珪化木も採ってきた物だと教えてくれましたが、場所までは判らないとのことでした。残念。
2017年10月27日
サクラマスの産卵場 赤川右岸支線田沢川
遡上のため跳ねたりしないか暫く眺めてましたが、確認できませんでした。

山形県の魚サクラマス。稚魚を幾ら放流していても、産卵時期に魚影を確認できないのは残念です。
2017年10月26日
サクラマスの産卵場 赤川右岸支線岩本川
2017年10月17日「サクラマスの産卵場 赤川右岸支線岩本川」へ行ってみました。
水量が多くこともあり、確認できませんでした。
水量が下がれば居るか居ないか判るでしょうから、
後日コンビニみやざきさんに尋ねることにします。

2017年10月22日
サクラマス産卵場 田沢川ダム下
2017年10月11日「サクラマス産卵場 田沢川ダム下」を再び観てきました。
サクラマスやヤマメ、イワナなどは確認できず、鯉が1尾泳いでました。
こんな状態ですから、サクラマスなどが産卵しても鯉に食われて終わりですね。
淵には鯉が群れており、釣るなり投網打つなりして、駆除してほしくなります。


2017年10月19日
県条例違反 愛好者に因る密漁と焚き火
彼らの地元月光川河口には2017年10月07日「鮭 密漁防止の上り旗」が掲げられていますが、
彼らが「シーバス釣りです」と主張しながら鮭を釣る密漁行為をしているから掲げられたのでしょうね。
だって、これだけ大層なウエアーでカッコ良く身を固めておきながら
「安心して下さい、釣ってませんよ」と主張するのですから、
確信犯ですと名乗っているようものですよ。常習性を禁じ得ず、全く酷い連中です。


彼らの蛮行は密漁行為だけではありません。鶴間池は鳥海国定公園であり、焚き火は禁止されています。
登山愛好者であれば、国定公園に限らず焚き火は当然として、直火も行なわないというのに、盛大に焚き火をしています。
鶴間池小屋の前は狭く、森林と小屋が火事になったらと考えなかったのでしょうか。
密漁、焚き火、しかも国定公園内で、言い訳しながらの確信的犯行。
自分たちの子供を連れてなら、マナーとモラルを教えるのも大人の努めです。
これが鳥海山麓に暮らす登山愛好者の認識かと思うと情けなくなります。

2017年10月17日
サクラマスの産卵場 赤川右岸支線岩本川
「こんびに みやざきの赤川鮎釣り&グルメ情報」がある東岩本地区を流れている。
店主いわく「毎年1〜3尾は産卵に姿をみせている」とのことだったが、今年は未だのようだ。

↑岩本川の魚止め。スーパー農道にも達してない集落内で魚止めとなる。赤川本線から数百メートルしかない。
↓赤川本線から直ぐにある床止め工。以前は砂礫に埋まって高低差が低かったけど
近年の局地的短時間豪雨の影響で本線が激しく増水するので、掘られてしまい、高低差が生じました。

あと10日ほどでサクラマスの姿が目撃されると良いのですが・・・。
2017年10月16日
サクラマスの産卵場 赤川右岸支線田沢川
2017年(平成29年) 8月25日(金)付け紙面より
サクラマスの遡上環境整備 すみかや餌場「石倉カゴ」設置
-----------------------------------------------------------------------------------
サクラマスが遡上(そじょう)する環境を整えようと、鶴岡市黒川の赤川右岸側の支流、田沢川で24日、魚のすみかや餌場となる「石倉カゴ」の設置作業が行われた。ワイヤの籠に川石を詰めたもので、護岸沿いに10基の石倉を設置。今後生息調査を続けていく。
赤川は天然サクラマスが遡上する川として知られ、河口から22キロの田沢川にも毎年遡上が見られたが、河川改修や護岸化が進み、魚類に好適な生息場が減ってきている。今回は、全国内水面漁業協同組合連合会、県内水面漁業協同組合連合が水産庁のウナギ生息環境改善支援事業として全国各地で石倉カゴを設置しモニタリングしている改善支援事業の一環で、赤川漁業協同組合(黒井晃組合長)がサクラマスにも応用して実施。全国で8カ所、計70基を設置するもので、県内では唯一。事業費は約240万円。
この日は午前8時半ごろから作業を開始。縦横各1メートル、幅50センチの直方体のネットに 20―40センチ程度の石が入った石倉(重さ約700―800キロ)を重機でつり上げ、護岸沿いに設置していった。川辺にはハグロトンボが飛び交う環境で、設置作業終了後はサクラマスの稚魚5000匹を放流した。
県内水面漁業協同組合連合会の大井明彦参事は「かつては大鳥までサクラマスが遡上したという。護岸工事は人間の生活を守るために大切だが、魚の生息場としては好適でない。石倉カゴの設置によってサクラマスが遡上する環境を整えたい」と話していた。
赤川水系の田沢川に魚のすみかとなる「石倉カゴ」を設置。サクラマスの遡上の増加につながる。
-----------------------------------------------------------------------------------
この時期を読んで赤川漁協の黒井組合長も頑張ったなと感心した。
赤川にもウナギが棲息しており、鶴岡淡水魚夢童の会を主宰する岡部夏雄さんは
「河川時で耕作している方から教えられて見に行ったら、1m近い大ウナギが毎日見られた」
と話してくれたことがあったし、大山の上池下池の水を抜くと必ずウナギが捕れたそうです。
ま、狙って採捕するほどの生息数はないにしろ棲息しているので、
日本海側の北方の生息地ということで水産庁のウナギ生息環境改善支援事業に引っ掛かったのだろう。
それをサクラマスにも応用させて田沢川で実施させたのは素晴らしい功績だ。
赤川水系におけるサクラマスの産卵場と産卵床の位置と数は、岡部さんが無茶苦茶子細に調査されており、
その資料を持って山形県のデーターとされている。
2000年10月に無明舎より自費出版された岡部夏雄著『庄内淡水魚探訪記』では、紙面の関係上、大まかに載っている。
田沢川には巨大な堰堤が在り、魚止めになっていたが、
試しに簡易魚道を試験的に設置したところサクラマスの遡上が確認されたので、
その後に現在在る立派な魚道が建設された経緯がある。これにも少し裏話があって・・・。
この田沢川はなかなかの暴れ川らしく、上流に床止め工が幾つもあるというのに、石がゴロゴロ流下してくる。
そのため簡易魚道の入口が石で埋まってしまうので、
魚道が埋まらないよう同集落在住の鶴岡淡水魚夢童の会の方がこまめに排出作業を行ないました。
そのお陰でサクラマスが遡上するようになったのが、石の流下は止らず、どんどん川が埋まってしまいました。
近年の雨の降り方は昔のようにシトシトと長く降らず、
ザー!っと激しく降ってパタリと止むゲリラ豪雨なので、流下した石が赤川本線まで流れていかないのです。
浅くなったことで葦が茂って川を塞ぎ、葦の上をチクチクする蔓が繁茂するので入川も困難な状況へ。
どんな場所でも川通しで調査している鶴岡淡水魚夢童の会が
『嫌だ。行きたくねー!』という気持ちが勝るほど川幅は狭くて、陽が当たらず日陰で暗いから鮎も居らず
とてもサクラマスが留まれるとは思えないほどでした。当時の川幅なんて40〜60cmくらしかなかったです。
それが今回の事業を活用したことで川原の葦を排除してくれたことで、赤川本線まで見通せるまでになりました。
たぶん数年でまた埋まってしまうかもしれませんが、その経緯は今後の課題に活かせることでしょう。

手を加えてない上流↓は、こんなにも葦に覆われています。流れが緩い下流がはどれだけ葦に覆われていたことか。

こんな拙いブログも10年経つと、ブログネタも資料となるようで、我ながら助かります。
2007年10月25日「産卵の季節」に載せた画像。

田沢川は山形県の管理河川。今回の事業は県とは無関係だから、
18平米(約5.4坪=10.9畳)でも河川占有権を申請しなければいけなかった様子。
サクラマスは県の魚なんだし、山形県が対応してもよいはずなのに、その無能振りが悲しく思える。
黒井組合長の頑張りに拍手。

2017年10月15日
マジな詐欺だった 鳥海ボトルアクア
2chで「典型的な詐欺商法」と言われた鳥海ボトルアクアを懲りずに、まだ商売をしていた。
2017年02月25日「商売としてのボトルアクアリウム」で記したように
個人や仲間内で楽しんでいるなら私は気にしませんが、
彼の飼育方法はメダカを虐待しており見過ごせません。
2017年08月25日「悲惨 .動物虐待! 鳥海ボトルアクア」

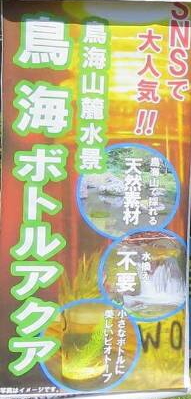
SNSで大人気!! だそうですが、2ch以外でも叩かれてるのに、何処で大人気なのかな?

『鳥海ボトルアクア』でネット検索すれば、上位5ツは下記で、
本人以外は鳥海ボトルアクアを評価しないサイトばかり。
鳥海ボトルアクア - ホーム | Facebook
https://ja-jp.facebook.com/chokaizan/
鳥海ボトルアクアについて。 : 志田園芸のブログ
http://admin.n-da.jp/admin/entry/edit/entry_id/748503
志田園芸のブログ
http://shidaengei.blog.jp/
鳥海ボトルアクア
天然資源は全てリサイクルや繁殖したものを使用しており生態系アドバイザーの指導の元制作を行っています。
http://chokaizan-aquarium.com/
庄内の日本桜草栽培日誌:2017年02月25日 商売としてのボトルアクアリウム
http://nihonsakurasou.n-da.jp/e723756.html
「志田園芸のブログ」を読むと、志田園芸さんが安価に販売していた白メダカを見つけたことは発端で
「安く仕入れられる!」「こいつで一儲けできないか?!」と企てたことが鳥海ボトルアクアの起源みたいです。
だからこいつはメダカに愛情がなく、しったかぶりしてあらゆるメダカの品種を羅列して、商品PRに利用したんですね。
志田さん宅に押し掛けたり、かなり痛い人物で、悪いことしている自覚もあるようで、確信犯的な要素満載。
「志田園芸のブログ」は必読です!!
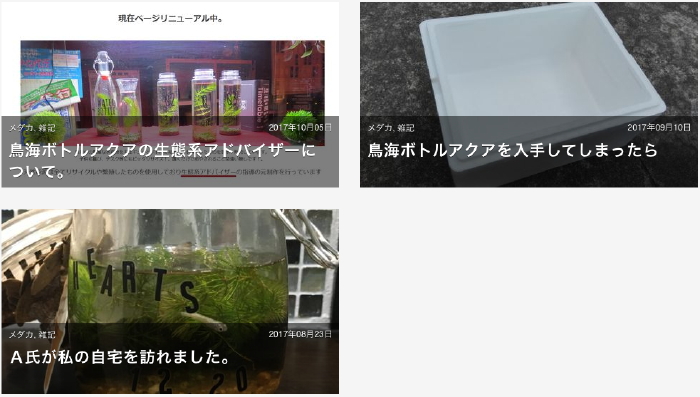
志田園芸のブログ 2017年10月05日「鳥海ボトルアクアの生態系アドバイザーについて。」に、
鶴岡市で植物と水生生物を調査している水野野生生物調査室代表の水野重紀氏が登場しています。
某村上氏は強引に面談を求め、自分を売り込み、名士たちの偉功を利用しようとしてたようで、水野氏の他に、
狩川の山澤清氏と
NPO鶴岡淡水魚夢童の会の岡部夏雄氏にコンタクトを取りました。
山澤と岡部両氏を一言で表すなら愚直。
自分にウソを付けないので徹底して調査研究をなされ、意見もズバッ!と言われます。
なので鳥海ボトルアクアなどに、一切関心されなかったことでしょう。また二人ともネットはやっています。
一方、水野氏は徹底した裏方さん。地域の自然関係の行事や企画に補佐として関わりますが、絶対に表には顔出しません。
水野氏も山澤、岡部両氏同様、フィールドワーク主体で活動されていますから、
鳥海ボトルアクアなどに感心して、関心を示し、関わりを持つはすがありません。
自ら裏方に徹してネットもやらないので、そこを某村上氏は利用したのでしょう。
上記サイトを読んで子細を知り納得です。
水野氏はネットやりませんが、水野氏の知り合いは大勢ネットをやるというのに
水野氏の名前を勝手に使い、バレないと思っていたのでしょうか。
荘内日報2017年7月15日で某村上氏は下記のように語っていますが、
『水野重紀さんから助言をいただきながら試行錯誤を繰り返し、云々』なんて
水野氏が否定されているのですから真っ赤なウソ。
彼はみんなを信用させるために水野氏を利用して商品の信憑性を高め、
騙して今も尚販売いるのですから、鳥海ボトルアクアはマジに詐欺商品だったわけです。
誤った飼育方法でメダカが死んで行く様を考えるだけで怒りが込み上げてきます。
メダカは横へ移動する魚なので、狭いボトルの中では生きていけません。
メダカは群れで棲息します。1尾だけでは警戒して怯えてしまい、餌も食わなくなります。
メダカは動物性が強い雑食性の魚です。藻だけでは生きていけません。
鳥海ボトルアクアのような詐欺商品を買わないようにしましょう。
また、既に所有されている方をみつけたら、メダカのためにも、正しい飼育方法を伝えてあげてください。
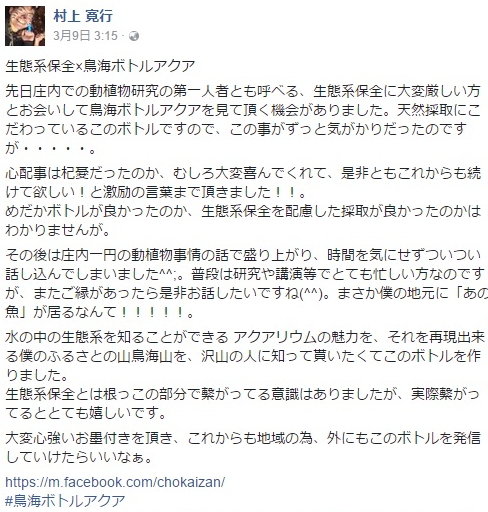

清川屋のイベントは中止になりました。
某村上氏が清川屋へ持ち込んだ鳥海ボトルアクアのメダカは、3日ともたず死んだそうです。
これらの件について某村上氏は一切何も語っていません。
また某村上氏は肩書きをコロコロ変えて、今は岩魚養殖屋になっています。
岩魚の養殖といっても、岩魚の稚魚を購入して飼育しているだけであり、繁殖はさせていません。
メダカにしても、最初は志田園芸さんのメダカを使い、売ってくれなくなると得たいの知れないメダカを使い、
その後はメダカ生息地から採捕してきたメダカを「庄内産メダカ」と唱って堂々と金儲けに利用しています。
販売に使うメダカを自分自身で繁殖させていませんし、今ではアカヒレまで使っているようです。
メダカのため、メダカの飼育方法を知らない方々のため、
天然のメダカをこんな商売に使わせないためにも、販売は止めてほしい。そして絶対購入しないようにしましょう!
2017年10月13日
17鮎釣り総括
落ち鮎そのものが激減して、行っても捕れないから、川漁師が川に出てないようです。
鉄橋下から三川町の赤川は川鵜で溢れているたしいから、落ち鮎を食い尽くしたのかも。
山形県では毎年鮎の産卵時期は禁漁期間を設け資源保護に努めており
今年は10月4日から10日まで禁漁となりましたが、
禁漁にしてしまうと川に人が現れなくなるので川鵜の独壇場になるから、なんか逆効果な気がします。
以前も書きましたが、春一番に遡上する一番鮎が秋までに大きく成長して、一番早く産卵する個体になるのですが、
その個体を川鵜に食われてしまうと、春一番に遡上する一番鮎が減少して、一番早く産卵する個体も激減します。
激減した一番早く産卵する個体も産卵場で群れているところを川鵜に食われてしまい、
春一番に遡上する一番鮎がますます減少して、一番早く産卵する個体もますます激減。
ますます激減した一番早く産卵する個体が産卵場で川鵜に食われてしまい・・・。
今の庄内地方の河川はこういう状況にあるので、大きな鮎が少なくて、今年はH2.6で通せました。
シーズン後半ナイロンでの泳がせ釣りをやっている時は
H2.5が欲しくなりました。それほどサイズが小さいかったのです。


今年一番大きな鮎は2017年09月14日「鮎は重さで語れ 今期最大164g」の164g。
160gの鮎は大きい方なので、本来なら凄く良い想い出に残るはずなんですが、使ったオトリは40g。
40gをオトリに使える水量で、40g+160gで200gしかないのから、H2.6で「えい、ヤッ!」と抜けました。
二番に大きな鮎が2017年09月02日「鮎は重さで語れ 今季最大144g」の144g。
前日釣った56gをオトリに114gを釣り、114gをオトリに132gを釣り、132gをオトリに144gをゲット。
「大きな鮎には大きなオトリ」の法則が通じた唯一の釣行となり、楽しかった。
でも釣果はこの3尾のみ。ポイントを知っているから良型をだせているという感じで、数が出ないのが今年の状況。
この3尾は友人に差し上げたところ、調理画像を送ってくれました。


164g、144gの後は136〜130g台が僅かでただけで、一番鮎の少なさを物語っていた。
解禁前は「今年は遡上数が多い!」と騒がれたが、遅い遡上個体が多かっただけの話し。
9月は元気に良く泳ぐオトリを得るのに苦労するのだが、未成熟な個体が多かったので、そこは楽だった。
川の中は元気に泳ぐ未成熟な個体が多い状況だから、40gのオトリに164gが反応して釣れたんだと思う。
「大きな鮎には大きなオトリ」の法則が通じないシーズンでもあった。
庄内地方の鮎の最初の産卵日は9月下旬の大潮に行なわれるので、
今年は9月19〜21日の大潮周りが最初の産卵日ではなかったと推察している。
『こんびに みやざきの赤川鮎釣り&グルメ情報』9月15日こん太の赤川情報 をみると
9月15日東橋上の淵に100羽近い川鵜が飛来したとのことで、
この頃一番鮎が下り始め、群れたところを襲われたんだと思う。
私はオモリを使った引き釣りがメインで、流れの強い場所深い場所を攻めて一番鮎を狙っているが、
釣れる場所を攻めて釣れる鮎を釣っているだけだから、釣れなければ粘らず移動するだけで、釣り方が非常に粗い。
それでも十分な釣果を得ることが出来たが、今年は瀬に鮎が入っておらず、流れの強い場所深い場所に鮎が居ない。
長年の癖で0.8〜0.5号のチビ玉を付けて止め泳がせで釣果を得るようになっていったが
ハタと気付いた。『流れが緩いんだから、オモリ要らないじゃね?! 』と。
複合メタル シマノのメタキング0.01〜0.03号を愛用していたが、
ナイロン0.4〜0.3号に張り替え、苦手な泳がせ釣りに転じると、あら不思議。意外と鮎居るじゃん♪
引き釣りや止め泳がせで釣れなかったり釣り返しが気かなった場所でも、狙った石周りで掛かるようになりました。
引き釣りと違って糸が張ってないので
ガガガン! ギュギューーーー!とダイレクトなアタリが伝わってこないのは残念でしたが、
狙った場所で掛けることができる悦びは大きかったです。
でもまあ、それだけ鮎が少なかった。獰猛な一番鮎が少なく、
遅く遡上してきた群れ鮎傾向の強い鮎が多かったということなんでしょうね。
今年の錨針は追いが弱いので4本錨がメイン。
アタリも弱いのでシワリがメイン。
以前は流れの中で掛かったので線径が太い重い小針を使っていましたが、
今年は強い流れに鮎が居ないので、線径が細い軽い大針を使いました。
40〜50gのオトリで100g前後を釣る今年の状況には合ってました。
またいつもなら7.5号止りですが、ケラレを防ぐには針先の間隔が離れていた方が良いのではないかと考え
がまかつのCueの8号(線径0.435mm)の4本錨を試したところ、非常に好い感じでした。
調べるとがまかつの鮎針には線径が細いのが多くて気になります。来年色々試したいですね。
2017年10月11日
サクラマス産卵場 田沢川ダム下
此処は禁漁区でサクラマスの産卵場でもあったが、此処何年もサクラマスの魚影を見ることはない。
相沢川は昔は地元に有名な鮎釣りの川だったが、今では泥被りで砂が堆積して石は泥被り。
河床は低下して淵もないから到底サクラマスが夏越できるとは思えない酷い有様である。
サクラマスが遡上していた当時、庄内地方におけるサクラマスとヤメメの産卵時期は10月10日頃と言われていたが
今では10月20日以降である。なので産卵場を見に行くのは未だちょっと早かったのが、天気が良いので見に行った次第。
ウグイとおぼしき小魚がキラッ。キラッ。っと単発的に藻を食んでいる姿が一箇所で見られただけで、魚ッ気は無かった。

サクラマスと入れ違いで姿を現したのは30〜40cmほどの鯉であった。
下流から遡上してきたのではなく、ダムから流下してきたのであろう。
鯉は雑食性で、砂の中のモノも食べるし、小魚も襲って喰う。
そんな魚がサクラマスやヤマメ、イワナの産卵場に居たのでは、
産み落とされた卵はもちろん、孵化した稚魚まで食われてしまう。
駆除してほしいが、此処は禁漁区だし、
管轄の最上第八漁協の鈴木組合長は最上川左岸の人間でもあり、
右岸支線には全く無関心でやる気が無くにべもない酷い人で、なんど言い争ったことか。
その鯉の姿が見えないと思ったら、下の淵に大きく成長して群れていた。
先ずはこの鯉たちを駆除しないと、サクラマスやヤマメ、イワナの資源保護が成り立たないぞ。

以前はダム下に居た鯉が、なんで下の淵に群れて居るのか不思議だった。
大きく成長したから水深が浅く感じて、深さある場所に移動したのかと思ったが、原因は川鵜の襲来だった。
この白く広いのが川鵜の糞の跡。だからウグイも僅かしか居なかったんだ。
鯉を駆除したら、テグスでも張って川鵜の襲来を防ぐ必要性もあるようだ。
川鵜は何所にでも現れ、月光川C&R区間の石の上も川鵜の糞で真っ白です。



